/MAT/LAW36 は Eps_p_max (破断塑性ひずみ) と、Eps_f (破断引張ひずみ) で指定して、要素を削除することができます。
しかし、一方で、次のように Eps_p_max も Eps_f も指定していないのに、要素が消えてしまうことがあります。
/MAT/PLAS_TAB/1
New MAT 1
# RHO_I
.008 0
# E Nu Eps_p_max Eps_t Eps_m
200000 .3 0 0 0
# N_funct F_smooth C_hard F_cut Eps_f VP
1 0 0 0 0 0
# fct_IDp Fscale Fct_IDE EInf CE
0 1 0 0 0
# func_ID1 func_ID2 func_ID3 func_ID4 func_ID5
1
# Fscale_1 Fscale_2 Fscale_3 Fscale_4 Fscale_5
1
# Eps_dot_1 Eps_dot_2 Eps_dot_3 Eps_dot_4 Eps_dot_5
0
え!?なんで消えてしまうのでしょう。
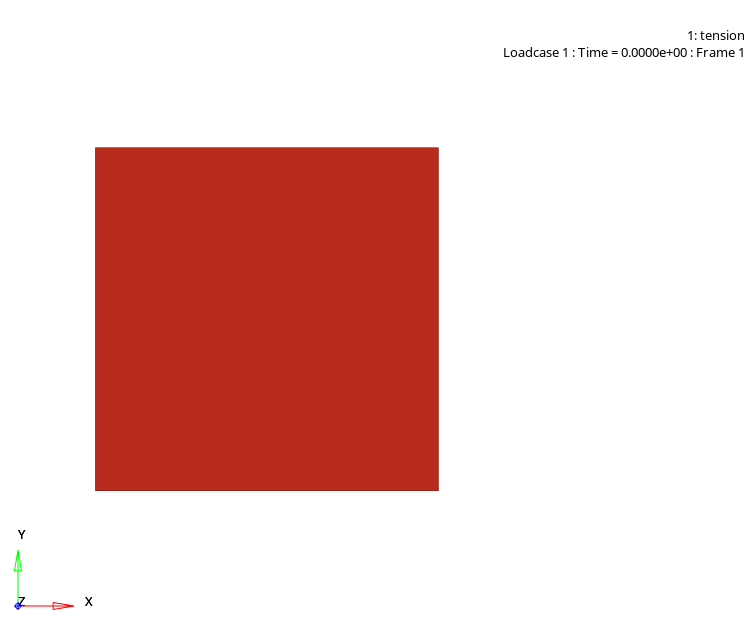
この場合は、降伏応力-塑性ひずみカーブに原因があります。
今回はこのように、初期降伏応力 200MPa, 塑性ひずみ 0.3 で 100MPa に低下するという設定です。Radioss は /FUNCT に書かれていない範囲は、最後の傾きでそのまま伸ばすので、この書き方だと塑性ひずみ 0.6 で応力 0MPa になります。
#---1----|----2----|----3----|----4----|----5----|----6----|----7----|----8----|----9----|---10----|
/FUNCT/1
stress_strain
# X Y
0 200
0.3 100
#---1----|----2----|----3----|----4----|----5----|----6----|----7----|----8----|----9----|---10----|
実は、降伏後応力が 0 になると、要素を削除する旨が、リファレンスに記述されています。
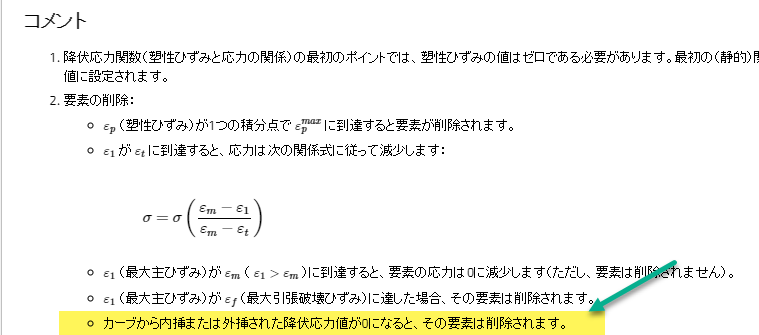
実は先ほどのモデルは、降伏応力が 0 となる塑性ひずみ 0.6 で要素が消えています。要素の真ん中の数字に着目。
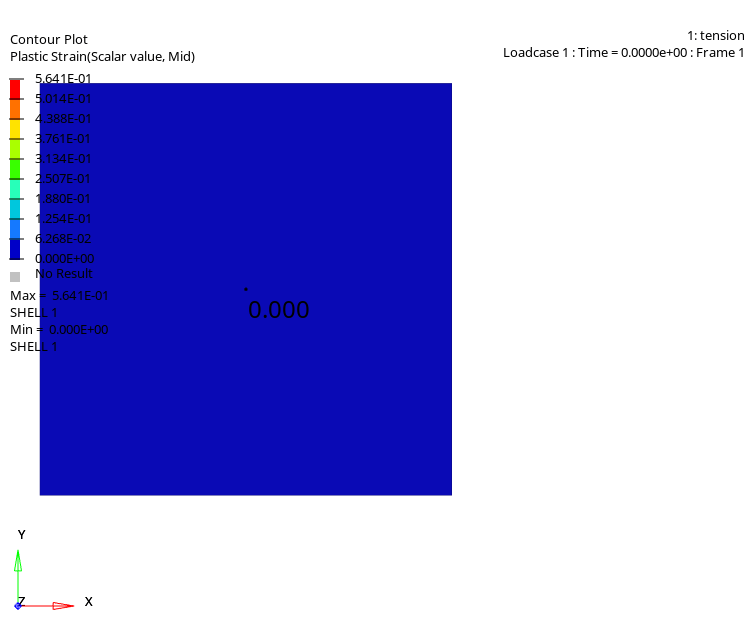
もし要素を消したくないのであれば、応力はどこかで下げ止まりにする必要があります。例えば、このようにすると、応力は塑性ひずみがどれだけ増えても降伏応力は 100MPa となり、要素は消えなくなります。
#---1----|----2----|----3----|----4----|----5----|----6----|----7----|----8----|----9----|---10----|
/FUNCT/1
stress_strain
# X Y
0 200
0.3 100
0.5 100
#---1----|----2----|----3----|----4----|----5----|----6----|----7----|----8----|----9----|---10----|
この記事に使った入力ファイルのダウンロード:
(初めの要素が消えるモデルです。/FUNCT/1 を変化させて、本当に消えなくなるか試してみてください)